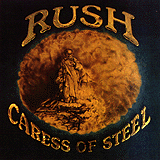 |
RUSH--Caress Of
Steel produced by RUSH and Terry Brown |
I am born
I am me
I am new
I am free
Look at me
I am young
Sight unseen
Life Unsung... (“The Fountain Of
Lamneth I. In The Valley”より)
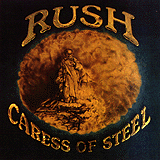 |
RUSH--Caress Of
Steel produced by RUSH and Terry Brown |
RUSHが20世紀中にリリースしたアルバム全20枚のなかで、個人的には一番聴くことがないアルバムが1975年リリースの3rd『CARESS
OF
STEEL』。RUSHの作品のなかでも『Billboard』のアルバム・チャート上での成績が一番悪い(最高148位)この作品、売り上げが悪くても、RUSHのいうバンドの歴史を振り返る際には、決して無視出来ない重要なアルバムなんだけどね。
前作『FLY BY
NIGHT』で哲人ニール・パートを迎えて、プログレ趣味の組曲スタイルの曲を演り始めたRUSH、この『CARESS
OF STEEL』では、12' 29''にも亘る“The
Necromancer”(邦題は“新しい日”)、さらに旧アナログのB面全てを使った大作“The
Fountain Of
Lamneth”(邦題は“ラムネスの泉”)の2曲の組曲を披露してます。ニール・パートを迎えてからプログレ化の道を進み出したRUSHの方向性は次の『2112』で明確になり、花開くんだけど、このアルバムではまだキレ味が無く、冗漫な印象が拭えないね。特に“The
Necromancer”のほう。“The Fountain Of
Lamneth”のほうは情景が目に浮かんでくるだけかなりマシ。
というところで、アルバム収録曲を順に見ていくと、旧アナログA面の1曲目はフランス革命から題材を取った“Bastille
Day”(邦題は“バスティーユ・デイ”)。バスチーユ監獄襲撃がフランス革命の狼煙だったよね(笑)。初期RUSHの代表曲で、初期のライヴのオープニング曲としてファンには馴染みのこの“Bastille
Day”、『CARESS OF
STEEL』はこの1曲だけだよね...とファンの間でもよく言われてる(笑)。ハードロックの佳曲。次の“I
Think I'm Going
Bald”には“老いてゆくのか”という素晴らし過ぎる邦題がついている(笑)。原題を直訳すると「僕はハゲてってるように思う」ってなるのかな(笑)。なんのヒネリもないアタリマエ過ぎのオールド・スタイルなハードロックだから、ファンのなかでも不人気ぶりでも一二を争います(笑)。3曲目の“Lakeside
Park”(邦題は“湖畔の想い出”)。この曲は初期の隠れた名曲に挙げておきたい! RUSHではこの後絶滅する(笑)青臭い青春モノです。あ、『HEMISPHERES』の“Circumstances”っつうのがあったネ(笑)。でも、この“Lakeside
Park”は青酸っぱい感じがするよ。爽やか(笑)。
小作3曲のあと、いよいよ組曲群。まずは“The
Necromancer”。この曲、リフの積み立てで出来た感じで、何かイマイチ、ストーリーが見えてこないんだよね。最後に前作にも登場した正義の味方『Prince
By-Tor』がやってきて、悪の魔術師をやっつける...という勧善懲悪モノの他愛のないストーリーです(笑)。
国内盤のライナーノーツで「B面の方に現在のRUSHの魅力がある」と大貫憲章センセイが力説してるとおり(大貫センセイも'75年当時のライナー、今も使われるの迷惑に思ってない?...笑)の旧アナログB面全てを使った力作の組曲、“The
Fountain Of
Lamneth”。この曲はもう片方の組曲とは違って、表現力豊か。「ラムネスの泉」を捜し求める旅に出る『僕』の物語。“No
One At The
Bridge”(邦題は“誰もいない橋”)での難破船のイメージや、愛しき女性・パナセアへのラヴ・ソング“Panacea”(邦題は“万病薬”)など情景が目に見えてきます。この曲を通じての学習体験が次の『2112』につながったと思うのは私だけではないハズ。このアルバムがあったから『2112』があった...と私は思ってるんだけど、ところが、アルバム通して聴くことは殆ど無いなあ。アルバムのもつ意義は大きいんだけど、魅力には乏しい...。近年のRUSHがこのアルバムからの曲をライヴで演らないせいからか、ファンも話題にしないし(笑)。
ところで、このアルバムには'75年当時に付けらてた邦題がそのまま残ってるんだけど、異様な邦題が今も放置されてるのは感心しません。ファンの間では“老いてゆくのか”(“I
Think I'm Going
Bald”)が評判悪いんだけど、コレ、私は容認します(笑)。真に許せないのが、“誰もいない橋”(“No
One At The
Bridge”)と“万病薬”(“Panacea”)でしょう。ストーリー読めば、『橋』じゃなくて『船橋』だって解るし、『Panacea』は『万病薬』っていう意味なのは辞書にあるとおりだけど、これまたストーリー読めば『パナセア』っていう女性のことだっていうことが解るハズ。邦題を付けた当時のレコード会社の担当ディレクターが歌詞読んでないってことがバレバレ。レコード会社の担当ディレクターですらこの体たらくなんだから、当時の日本のロック・ファンがRUSHに無関心だったのはある意味しょうがないねェ...。
なお、この『CARESS OF STEEL』からRUSH御用達デザイナー・Hugh
Symeが、アルバムのアートワークを担当し始めました。
('01.6.30)