
JASRACがうるさいので、歌詞と訳詞は省略させていただきます。


2007年12月(第87回)...U2“プライド”(“Pride
(In The Name Of Love)”)より
アルバム『焔(ほのお)』(『The Unforgettable Fire』)収録...1984年作
【コメント】
U2が1984年の末にリリースした4thアルバム『焔(ほのお)』に収録され、このアルバムからの1stシングルとしてリリースされたU2の代表曲の1つ。
前作『WAR(闘)』のヒットで、アイルランドのいちローカル・バンドからワールドワイドな人気バンドへの一歩を踏み出した彼らが、次のステップに進んだアルバムが『焔(ほのお)』。それまでのU2が、彼らの故郷・アイルランドの極寒を思わせるような冷たく、鋭い感覚のあるサウンドが持ち味だったとすれば、このアルバムから1992年の『ZOOROPA』までは一貫として暖かく弛緩する方向に進んでいった。その結果として、アイルランド出身のバンドとして空前の大成功を収めたロック・バンドに成長し、今もシーンに君臨し続けている。この曲でも、それまでの代表曲だった“New
Year's Day”や“Sunday Bloody
Sunday”という曲からには無かった暖かさが感じ取れる。
U2の代表曲というと今や“With Or Wthout
You”という声が圧倒的だろうけど、私はこちらのほうが好きだし、この曲のヒットがあったからこそ“With
Or Wthout
You”が出来たと勝手に思っとります。それくらい好きな曲。
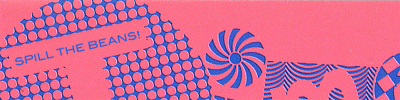
2007年11月(第86回)...ザ・タイマーズ“偽善者”より
アルバム『ザ・タイマーズ』収録...1989年作
【コメント】
1989年に登場した謎(?)の4人組、ザ・タイマーズのデビュー盤に収録されている曲。ザ・タイマーズのリーダーでヴォーカル&ギターのZERRYさんは、何故かRCサクセションの(当時)忌野清志郎とそっくり!...ということが当時から話題になってました(爆笑〜〜〜!!!)。
ザ・タイマーズといえば、10月13日深夜放送分のフジテレビの深夜のTV音楽番組『ヒットスタジオR&N』で、突然演奏予定曲目を変更し、RCサクセションが1988年にリリースした“ラブ・ミー・テンダー”などの曲を放送禁止としたFM東京を♪FM東京〜バカのラジオ〜などと罵倒する曲をゲリラ的に演奏したことが有名ですが(笑)、その時、本来ならば演奏されるハズだったのが、この曲です。

2007年10月(第85回)...エコーベリー“キング・オブ・ザ・カーブ”(“King
Of The Kerb”)より
アルバム『オン』(『On』)収録...1995年作
【コメント】
1990年代中盤に隆盛を誇ったブリット・ポップ・ブームの頃にデビューしたバンド、エコーベリーが1995年にリリースした2nd収録曲で、シングルとしてもリリースされた。
エコーベリーは、在英インド人の上流家庭に産まれ、厳しい「お嬢様教育」を受けたという女性ヴォーカリスト、ソニア・オーロラ・マダンを看板に立てた男女混成5人組。他にもアフリカ系の女性ギタリスト、デビー・スミスも居て、多様な人種によるバンド編成も特徴的だった。
ブリット・ポップ・ブームの頃には、主に音楽雑誌『rockin'
on』のプッシュ、しかも、音楽性に重きを置くよりも「ソニア、可愛〜〜〜い☆!」(今ならおそらく「ソニア、萌え〜〜〜☆!」になってただろう...苦笑)的なミーハーなプッシュのされ方で日本でも人気バンドとなった。デビュー作『エヴリワンズ・ガット・ワン』、そして2nd『オン』リリース時には来日公演を行えるくらいの人気があったが、ブリット・ポップの退潮が始まると、彼女たちも他の多くのバンドと同じく、人気が凋落し、メジャーからドロップしてしまった。しかし、彼女たちが他のブリット・ポップ・バンドと違うのは、メンバー・チェンジを経て、活動の場をインディーズに移しても今でもバンドが存続してることである。昔、あれだけ彼女たちのことを持ち上げていたヤツらは、今や彼女たちの活動状況を一行たりとも報道しないが...。
この曲で聴けるソニアの前向きな歌を聴くと、こういう歌を歌えるひとだからこそ不遇に耐えて今もバンドが続けられるんだな...と思ってしまう。

2007年9月(第84回)...カーディガンズ“ラヴフール”(“Lovefool”)より
アルバム『ファースト・バンド・オン・ザ・ムーン』(『First Of The
Moon』)収録...1996年作
【コメント】
女性ヴォーカリストのニーナ・パーションを看板に据えたスウェーディッシュ・ポップの代名詞的なバンドのカーディガンズの3rdアルバムに収録されている曲で、レオナルド・ディカプリオ主演映画の『ロミオ+ジュリエット』の挿入歌になり世界的大ヒットを記録した。
1995年頃、いわゆる『渋谷系』と呼ばれるオシャレなポップ・ミュージックがブームとなり、この時に人気を集めた代表格が彼女たち。2ndアルバムの『ライフ』からの“Carnival”のヒットを機に、洋楽界は一種スウェーディッシュ・ポップ・ブームに沸く。彼女たちの人気は『ビッグ・イン・ジャパン』なものでは無く、欧米でも成功を収め、その頂点といえるのがこの曲の大ヒット。当時の『Billboard』ではシングル・カットされていない曲を『HOT
100』にはランク・インさせない方針だったためレギュラー・チャートでは1位にはなってない(どころか、チャート・インすらしていない)が、1996年の年間エアプレイ・チャートで1位になるほどとてつもない大ヒットだった。日本でもこの曲のヒット後のジャパン・ツアーは日本武道館を含む大規模なものとなった。
その後、スウェーディッシュ・ポップ・ブームも去り、彼女たちの人気も最盛期の半分以下となってしまったが、今でも地道に活動を続けてます。
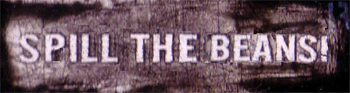
2007年8月(第83回)...プロディジー“ファイアスターター”(“Firestarter”)より
アルバム『ザ・ファット・オブ・ザ・ランド』(『The Fat Of The
Land』)収録...1997年作
【コメント】
熱狂のさなかには「どうして自分はこんなに熱狂してるんだろう?」と一切考えようともせず、熱狂がすっかり醒めてしまってから「どうして自分はあんなモノに夢中になってたんだろう?」と自問したくなることがロックの世界には多々あります。1997年のプロディジー・ブームはその典型的な例。3rdアルバム『ザ・ファット・オブ・ザ・ランド』リリース前から洋楽メディアはプロディジーの話題で持ちきりで、デビュー時や2ndアルバム・リリース時に彼らの記事を載せたこともないようなメディアまでもが彼らのことをもて囃し、一度みたら忘れられないほどのインパクトを放ったキース・フリントの逆モヒカン・ヘアの効果もあり、「プロディジーの良さが分からない奴はロックじゃない」といった風潮がすっかり出来上がってしまいました。1997年に山梨県の天神山スキー場で開催された『伝説』の第1回目の『FUJI
ROCK
FESTIVAL』(以下、フジ・ロック)への出演も決まり、あいにく台風の直撃を喰らって彼らが出演する予定だった2日目は中止となったものの、1日目のレイジ・アゲインスト・ザ・マシーンのステージにキースとマキシム・リアリティーが飛び入りするなど、第1回目の『FUJI
ROCK
FESTIVAL』が『伝説』化するのにひと役買ったり...と、当時の彼らは何をやっても上手くゆく『百戦百勝』のような状態。このまま彼らの勢いはしばらく続くか...と当時、誰もが思ってたでしょう。しかし...。次のアルバムのリリースまで7年もかかると、流石に世間の彼らに対する熱はすっかり醒めてしまいました。私も彼らの4thアルバム、買ってません...(苦笑)。

2007年7月(第82回)...サザン・カルチャー・オン・ザ・スキッズ“グリーンバック・フライ”(“Greenback
Fly”)より
アルバム『ダート・トラック・デイト』(『Dirt Track
Date』)収録...1995年作
【コメント】
「落ち目の南部文化」という意味の自虐的なバンド名をもつ、ノース・キャロナイナ州を拠点とする男女混合3人組のロック・バンド、サザン・カルチャー・オン・ザ・スキッズの1995年リリースのメジャー・デビュー・アルバム『ダート・トラック・デイト』収録曲。このアルバムは『CMJ』チャートの上位に喰い込み、その甲斐あってか日本でも1995年の年末にリリース。私をはじめとする一部好事家(苦笑)はこの当時から彼らに注目してたけど、当時のミュージック・シーンにおいては彼らのことはそれほど話題にならなかった。彼らの名前が一躍有名になったのは、1997年に山梨県の天神山スキー場で開催された第1回目の『FUJI
ROCK
FESTIVAL』(以下、フジ・ロック)に出演してから。日本初の画期的ロック・フェスティヴァルとして注目を集めたものの、台風の直撃を喰らって2日目が中止になるなどサンザンな結果に終わりつつも、それゆえに伝説となり今日まで語り継がれる初回フジ・ロック第1日目の栄えあるオープニング・アクトを務めたのが、彼ら。私もあの天神山スキー場のフィールドに居たので、よく憶えてます(苦笑)。オープニング・アクトの(それまでほとんど無名に近かった)彼らがステージに登場し、演奏を始めた途端、観客たちはいきなり大いに盛り上がり始め、3曲目にこの曲が演奏されると観客がステージ前にどんどん押し寄せため、バンドはこの曲の演奏を中断。アタマから演奏し直したものの、それでも観客が盛り上がり過ぎてステージ前が危険な状態となったため、また演奏中断を余儀なくされました。「3度目の正直」でようやくこの曲を完奏させてもらえた彼ら(苦笑)。第1回目の『フジ・ロック』にはいろんな想い出がありますが、天神山スキー場の『フジ・ロック』と聞いて真っ先に思い出すのは、私の場合、実は、この曲だったりします。
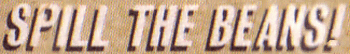
2007年6月(第81回)...フー・ファイターズ“ジズ・イズ・ア・コール”(“This
Is A Call”)より
アルバム『フー・ファイターズ』(『Foo Fighters』)収録...1995年作
【コメント】
ニルヴァーナのドラマー、デイヴ・グロールのバンド、フー・ファイターズが、カートの死の翌年(1995年)にリリースしたデビュー・アルバムの1曲目に収録されている曲。
『グランジ・ブーム』を巻き起こしてロックの世界の新しい扉を開き、一躍ロック・アイコンに祭り上げられたカート・コバーンの猟銃自殺により悲劇的な終末をたどったニルヴァーナ。多くのロック・ファンが心を痛めるなかに射した一筋の光が、ドラマーだったデイヴのニュー・バンド。しかもドラマーからギタリスト/ヴォーカルに『転向』し、フロントマンを務めるという。ニルヴァーナ・ファンはこのニュースに期待を寄せ、デイヴが新たに始めると音楽の全貌が明らかになるのを心待ちにしていた(と、思う)。リリースされたデビュー・アルバムは、ニルヴァーナの音楽にあるような陰鬱さは無く、突き抜けた明るさと希望に満ちた前向きさにあふれていた。ニルヴァーナのファンの多くは、このアルバムを聴いた時ぐらいはアタマのなかからカートの悲劇のことを忘れたり、悲しみが薄れたりしたんじゃないだろうか...と、私は思ってます。
このデビュー・アルバムはほとんどデイヴひとりでレコーディングしたものであり、その後、ネイル・デイトンとパット・スメア、ウィリアム・ゴールドスミスを加え、正式にフー・ファイターズというバンドとしてやっていくようになりますが、度重なるメンバー・チェンジにより、今では顔ぶれはだいぶ変わっています(苦笑)。

2007年5月(第80回)...レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン“ブルズ・オン・パレード”(“Bulls
On Parade”)より
アルバム『イーヴィル・エンパイア』(『Evil Empire』)収録...1996年作
【コメント】
ハードコアにラップを持ち込んで成功した、'90年代を代表するヘヴィー・ロック・バンドのレイジ・アゲインスト・ザ・マシーン(以下、RATM)の1996年発表の2ndに収録されてる曲。
私がRATMの音楽を聴いたのは、実はこの2ndからであって、衝撃的なアルバムのアートワークで知られるデビュー・アルバムの発表時には完璧にノー・マークでした。そんな彼らに興味を持ったのは、『ロラパルーザ』での例のアンチPMRCによる全裸演奏ボイコット...では無くて(苦笑)、ま、確かに『CROSSBEAT』1996年4月号掲載の写真はインパクトありましたが(苦笑)...デビュー作の評判とセールスが良かったからです。しかも、この2ndは『Billborad』のアルバム・チャートで初登場1位を記録するヒット・アルバムだったし。で、実際に聴いてみたところ、私は音楽の三要素(リズム、メロディー、ハーモニー)のうちメロディーが無いと受け付けない人間であり、本来ならザックのラップ・ヴォーカルにはメロディーが無いので受け付けないハズなんですが、バックの3人が出す「オケ」にメロディーがあるので、すぐに受け入れました(笑)。
このアルバム・リリース後、RATMの人気はうなぎ上りとなり、翌1997年の伝説の第1回目の『フジ・ロック』でもこの曲を演奏してくれました。このままずっとロック・シーンをリードする存在であり続けるかと思いきや、3rdリリース後にザックが電撃脱退! 残された3人は元・サウンドガーデンのクリス・コーネルとオーディオスレイヴを結成しますが、これまた3rdリリース後にポシャってしまいました。2007年4月27〜29日の『コーチェラ・フェスティバル』出演のため再結成されたらしいRATMですが、この再結成が一時的なものなのか、永続的なものなのか、今後の展開が気になるところです。
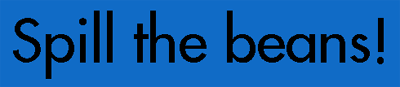
2007年4月(第79回)...ウィーザー“マイ・ネーム・イズ・ジョナス”(“My
Name Is Jonas”)より
アルバム『ウィーザー』(『Weezer』)収録...1994年作
【コメント】
ウィーザーの1994年5月リリースのデビュー・アルバム『ウィーザー』(通称『ブルー・アルバム)は彼らの最高傑作との呼び声も高く、後進に多大な影響を与え、多くのフォロワーを生み出した。そんな傑作アルバムの1曲目に収録されている曲。
今の彼らの人気からすると考えられないことかもしれないけど、このアルバムの日本盤は『Billboard』のアルバム・チャートで上位にランクされ、アメリカでブレイクした1995年の春になってようやくリリースされた。私もこのアルバムを聴いたのは日本盤がリリースされる1995年の3月頃で、私にとっては大学を卒業し、社会人への過渡期にあたる時期。当時はマイカーも持ってなかったので、学生生活を送ってた松本から就職先のある富山までの行き帰りは全て片道5時間の鉄道を使ってた。普通は4月から社会人生活が始まるものだけど、私の場合は勤務先が繁忙期だったため3月中からバイト扱いで会社で働き、かといって卒業式や引っ越しなどもあっため、頻繁に松本と富山の間を往復してた。その移動中にポータブルCDプレイヤーでよく聴いてたのがこのアルバム。今でもこのアルバムを聴くと、学生生活を終えて社会人生活に踏み出したあの頃を思い出します(苦笑)。
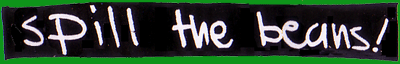
2007年3月(第78回)...グリーン・デイ“2000ライト・イヤーズ・アウェイ”(“2000
Light Years Away”)より
アルバム『カープランク』(『Kerplunk!』)収録...1992年作
【コメント】
グリーン・デイが1994年のメジャー・デビュー前に残した2枚のアルバムのうち、2nd『カープランク』の1曲目に収録されてる曲。初期の彼らの代表曲の1つで、かつてのライヴでの主要レパートリーのひとつでした。
私が彼らのライヴを初めて観たのは、1998年3月のジャパン・ツアー(『ニムロッド』リリース時)。グリーン・デイのライヴはその後も何度か観ていて、毎回印象深い出来事があったんだけど、この時のライヴが一番印象に残ってます。この曲はライヴの中盤に披露され、ビリーが楽器を手放して客席に降りて観客を煽ったりしていたので、印象深かった1998年3月のジャパン・ツアー時のライヴのなかでも、この曲の時の記憶が一番鮮明に残ってます(苦笑)。
最近の彼らのライヴでは、この曲の出番があまり無いようですが、またライヴで聴いてみたいと思ってます。
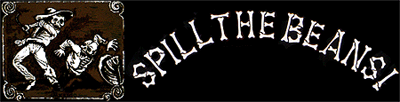
2007年2月(第77回)...オフスプリング“ザ・ミーニング・オブ・ライフ”(“The
Meaning Of Life”)より
アルバム『イクスネイ・オン・ジ・オンブレ』(『Ixnay On The
Hombre』)収録...1997年作
【コメント】
アメリカのカリフォルニア州オレンジ・カウンティー出身のメロコア・バンド、オフスプリングのメジャー・デビュー・アルバムとなる4th『イクスネイ・オン・ジ・オンブレ』の2曲目に収録(オープニングの“Disclaimer”は、ジェロ・ビアフラによるM.C.のため、実質は1曲目)。
前作『スマッシュ』の大ヒット後、『Epitaph』を離れ『Sony』に移籍。注目を集めるなかリリースされた4thは、『スマッシュ』の路線を堅持しつつも、『Epitaph』の重鎮、バッド・レリジョンを思わせる硬派な面も色濃い。特に、この“The
Meaning Of
Life”は、バッド・レリジョンの名曲“Generator”とメロディーと曲の構成、♪oh〜yeah〜oh〜yeah〜のフレーズなどがソックリなため、余計そう思うのかもしれません(苦笑)。
彼らが♪give it me
baby〜aha〜aha~...と歌い、『おバカ・バンド』扱いされ始めるのは、次のアルバムからです(苦笑)。

2007年1月(第76回)...バッド・レリジョン“ザ・ライ”(“The
Lie”)より
アルバム『ザ・プロセス・オヴ・ビリーフ』(『The Process Of
Belief』)収録...2002年作
【コメント】
『メロコアの帝王』と呼ばれるバッド・レリジョンの通算12枚目のアルバムにして、1994年の『ストレンジャー・ザン・フィクション』を最後に『Epitaph』レーベルの社長業に専念するためバンドを離れてたMr.ブレットがバンドに復帰して製作した放った『起死回生作』。
ヴォーカリストのグレッグ・グラフィンが生物学博士号を取得してるため、格調の高い歌詞が特徴の彼ら、この曲も2分18秒で終わってしまうけど、たった2分余りでリスナーに突き付ける内容は、実に「深い」のです。