
JASRACがうるさいので、歌詞と訳詞は省略させていただきます。


2006年12月(第75回)...ガンズ・アンド・ローゼズ“ペイシェンス”(“Patience”)より
アルバム『G N' Rライズ』(『G N' R
Lies』)収録...1988年作
【コメント】
1987年のデビュー・アルバム『アペタイト・フォー・デストラクション』の世界的な大ヒットで一躍時代の寵児となったガンズ・アンド・ローゼズ(以下、ガンズ)が1988年にリリースしたミニ・アルバム『G
N'
Rライズ』に収録されてる曲で、シングル・カットされて全米チャート(『Billboard』のシングル・チャート)で最高位4位のヒットを記録した。当時、バッド・ボーイズ・ロックン・ロールにパンクの勢いを持ち込んで凶暴化したサウンドとW・アクセル・ローズのハイ・トーン・ヴォーカルを武器にして注目を集めてた彼らだけど、この曲“Patience”はアコースティックなバラード曲。『G
N'
Rライズ』というアルバムじたい、インディ−ズ時代のライヴ音源(旧アナログA面)と新録のアコースティック曲(同B面)という構成で、アコースティックの新録曲は彼らがもつ他の一面と幅広い音楽性、引き出しの多さをアピールするのに成功。誰もがガンズはあと10年は安泰だと思ったハズだ。だけど、ドラマーのスティーヴン・アドラーを追い出した頃から雲行きがアヤしくなり、1991年に2枚同時発売アルバム『ユーズ・ユア・イリュージョンI』と『ユーズ・ユア・イリュージョンII』を出したものの、主要ソングライターのイジー・ストラドリンが脱退。次のオリジナル・スタジオ録音盤の製作に取りかかるもアクセルの完璧主義が災いしてか時間がかかり過ぎ、スラッシュ、ダフ・マッケイガンもサイド・プロジェクトを経て、やがてはガンズから離脱。残されたオリジナル・メンバーはアクセルのみとなり、タイトルだけは前々からアナウンスされてる新作『チャイニーズ・デモクラシー』もなかなか仕上がらず、2002年に久しぶりに日本に来てライヴを演って(『サマソニ』出演)ファンに「今度こそは!」と期待させておきながらその後の展望が開けないまま2006年も終わろうとしている。ファンはいったいいつまで「がまん」しなきゃいけないんだろう?

2006年11月(第74回)...MEN'S
5“"ヘーコキ"ましたね”より
アルバム『SOUL SKINSHIP』収録...1994年作
【コメント】
5人組のコミック・バンド、MEN'S
5(メンズ・ファイヴ)が1994年の有線放送大賞新人賞を獲得するに至ったスマッシュ・ヒット曲。
学校の音楽の授業で歌う“小さな秋みつけた”を思わせるピアノ、そしてダーク・ダックスやデューク・エイセスばりの男声ハーモニー(?)をもって「おなら」について歌うこの曲は有線放送そしてラジオを中心に人気が広まった。1994年当時私は信州大学理学部化学科4年で卒業研究の真っただなか。研究室ではいつもFM長野がかけっ放しになってたんだけど、平日午後からの『ヒルサイド・アヴェニュー』という番組のパーソナリティー(小川もこ)がこの曲を気に入って番組で頻繁にかけてたので、そのうち研究室仲間の間でも人気爆発。卒業の時の打ち上げの飲み会ではカラオケで歌う者まで出現!(私のことだけど...爆笑〜!!!)
今ではこの歌は世間的に省みられることも少なくなり、私も殆ど歌うことが無くなりましたが、この曲は間違いなく私の大学時の大切な想い出のうちの一つです(爆笑〜!!!)。

2006年10月(第73回)...サンタナ“ホールド・オン”(“Hold
On”)より
アルバム『シャンゴ』(『Shango』)収録...1982年作
【コメント】
1960年代から活動を続けるラテン・ロック界の重鎮・カルロス・サンタナ率いるサンタナが1982年にリリースしたアルバム『シャンゴ』からのシングルで、1982年の秋頃にヒットした曲。
デビュー以来、ヒット作を連発してたスーパーバンド・サンタナが低迷期に入り出す頃のアルバムで、今年リリースされたサンタナの紙ジャケ再発シリーズの仲間にも入らなかったことからも、このアルバムに対する巷の評価が良く解る(苦笑)。でも、この曲がヒットした1982年といえば、私が洋楽を聴き始めた年に当たり、あのサンタナが「つまらんアルバム(曲)を出した」という評価や偏見に惑わされず、この曲を「ヒット・チャートをにぎわす、いちヒット曲」として素直に聴けました。洋楽にハマり始め、聴く曲聴く曲すべてが珍しく、光り輝いてたもんなぁ〜(苦笑)。
1982年といえば、私が『笑福亭鶴光のオールナイト・ニッポン』を聴き始めた年にも当たります(爆笑〜!!!)。この「品性下劣」な番組を聴くために、夜8時に一度寝て、目覚まし時計で夜中1時に起きる...などの努力をしてたなぁ〜(苦笑)。そんな『鶴光のオールナイト・ニッポン』で、この曲がよくかかってたのが今でも記憶によく残ってるんだけど、この曲の選曲は、鶴光自身がやってたのか、今もって、謎(苦笑)。ず〜〜〜っと低迷期が続いてたサンタナが世紀末の1999年になってから人気が再爆発し、21世紀に入ってからもその人気を維持してんのも、謎だけど...(苦笑)。
<追記(2024.10.8)>
この曲は、RUSHの作品を本国・カナダでリリースしてたインディー・レーベル『Anthem』所属のシンガー/ソングライター、イアン・トーマスが1981年にリリースしたアルバム『The
Runner』からのシングル曲のカヴァーでした。この曲が実はカヴァーだったなんて...。40年経ってようやく知った真実...(汗)。
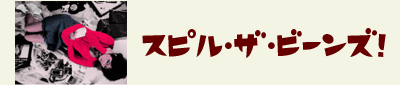
2006年9月(第72回)...ASOBI
SEKSU“I'm Happy But You Don't Like Me”より
アルバム『Asobi Seksu』収録...2004年作
【コメント】
日本人女性ヴォーカリスト/キーボード・プレイヤー・Yuki
Chikudateを中心としたニューヨークを拠点とする4人組・ASOBI
SEKSUが2004年にリリースしたデビュー・アルバムの1曲目に収められている曲。このデビュー作は、2004年5月頃に『CMJ』のカレッジ・チャートの上位に喰い込み、好事家の間で(笑)話題になってた。私がこのアルバムを初めて聴いたのはリリースから1年以上も経った2005年の9月のこと。ちょうど長女のポッポが生まれたばかりで、ポッポと弟子が居る弟子の実家に通うクルマのなかでヘヴィー・ローテーションとなってました(笑)。この曲を聴くと、ポッポの顔を見に弟子の実家に通った頃を思い出します(爆笑〜!!!)。
彼女たちの曲の半分くらいは日本語で歌われているんだけど、この“I'm
Happy But You Don't Like
Me”も御覧のとおり全部日本語の歌詞。しかも、この内容(苦笑)。実家からポッポと一緒にキャラメルハウスに戻った弟子がこの曲を聴いて「もっと前向きな歌を歌えないのかな? このひとたち...」とコメントしたのも、今となっては想い出だなぁ〜(爆笑〜!!!)。
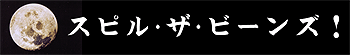
2006年8月(第71回)...天野月子“B.G.〜Black
Guitar+Berry Garden〜”より
アルバム『Sharon Stones』収録...2002年作
【コメント】
「つっこ」こと天野月子の2002年6月リリースのデビュー・アルバム『Sharon
Stones』に収録されてる曲で、もともとは2001年秋にリリースされた2ndシングル曲(インディーズの『音倉レコード』からのリリース)で、天野月子もつポップな側面がよく出てる曲で、つっこファンの間でも人気の高い曲。ライヴの定番ともいえる曲です(演らない時もあるケド)。
2002年の夏といえば『Sharon
Stones』のアルバムを聴いてばかりいて、8月10日からの南アルプス登山(北岳―聖岳
;
山中6泊7日)のお供にもしてました。この曲を聴くと、この時の二軒小屋ロッジのキャンプサイトの光景が鮮明に甦ってきます(笑)。超・私的な話でゴメンナサイ...(苦笑)。
![]()
2006年7月(第70回)...デビー・ギブソン“フーリッシュ・ビート”(“Foolish
Beat”)より
アルバム『アウト・オブ・ザ・ブルー』(『Out Of The
Blue』)収録...1987年作
【コメント】
1987年からの'80年代末期のミュージック・シーンのムーヴメントのひとつに、ティーンズ・アイドルの活躍というのがありました。“I
Think We're Alone Now”(“ふたりの世界”)が全米No.
1に輝く大ヒットとなり、ブームの火付け役になったティファニー('87年当事、16歳)、後に「シャニース」というシンプルな芸名になってヒットを飛ばすシャニース・ウィルソン('87年当事、14歳)、後のバックストリート・ボーイズなどの活躍の原形になった???ボーイズ・グループのニュー・キッズ・オン・ザ・ブロックなどなど。そのティーンズ・アイドル・ブームのなか、自分で作詞・作曲もして、キーボードも弾けちゃう16歳の天才少女として脚光を浴び、デビュー・アルバム『アウト・オブ・ザ・ブルー』を全米だけで300万枚売ったのがデビー・ギブソン。ブームの火付け役・ティファニーに遅れること約半年の1988年夏、デビー・ギブソンもこの“Foolish
Beat”が全米No.1に輝き、翌1989年の2nd『エレクトリック・ユース』から“Lost
In Your
Eyes”が全米No.1。早くも人気に翳りの出てきたティファニーをよそに快進撃を続けるデビーに「やっぱり作詞・作曲もして、キーボードも弾けちゃう娘は違うのお...」と感心してたものです。しかし、'80年代も終わり、'90年代に入った途端、脳天気なティーンズ・ポップはグランジ&オルタナ・ブームに駆除され、デビーも'90年代半ばからはメジャー契約からドロップしてしまいました(苦笑)。
当時16歳のデビーのはちきれんばかりの若さが詰まったデビュー・アルバムに入ってる曲の中では「異色作」ともいえる失恋を扱ったバラードですが、1988年の夏はこの曲をよく聴いてました。そして部屋にはデビー・ギブソンのポスターも貼ってました(爆笑〜!!!)

2006年6月(第69回)...RUSH“スウィート・ミラクル”(“Sweet
Miracle”)より
アルバム『ヴェイパー・トレイルズ』(『Vapor
Trails』)収録...2002年作
【コメント】
RUSHが2002年にリリースした17作目のオリジナル・スタジオ録音盤『ヴェイパー・トレイルズ』収録曲。この作品の前のスタジオ録音盤『テスト・フォー・エコー』は1996年リリースだったから、6年ぶりのアルバム。彼らのキャリアからするとこれまでに例をみないほど長いインターヴァルが開いた。その理由とは...。
『テスト・フォー・エコー』に伴うツアー終了後、バンドの作詞家であるドラマーのニール・パートに次々と悲劇が襲う。まずは、一人娘のセレナさんの交通事故死。さらに、妻のジャクリーンさんのガン死。愛する家族を次々と失ったショックのあまり、ニールはしばらくの間音楽活動から遠ざかってしまう。バンドが解散してもおかしくない危機。しかし、やがて傷心のニールに転機が訪れる。写真家のキャリーさんとの出会い、そして、再婚。再婚により、心の傷が癒えたニールはRUSHとしての活動を再開する。こうして出来上がった作品が『ヴェイパー・トレイルズ』なんだけど、こういうエピソードを念頭にこの曲の歌詞をみると、「絶望からの回生」が歌われてるようで、なんか、こう、胸にグッとこみあげてくるモノがあります。
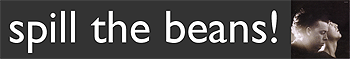
2006年5月(第68回)...ティアーズ・フォー・フィアーズ“ルール・ザ・ワールド”(“Everybody
Wants To Rule The World”)より
アルバム『シャウト』(『Songs From The Big Chair』)収録...1985年作
【コメント】
ローランド・オーザバルとカート・スミスによる英国のポップ・デュオ、ティアーズ・フォー・フィアーズが1985年にリリースした2ndアルバム『シャウト』に収録去れてる曲で、全米No.
1にも輝いた彼らの代表曲の1つ。日本ではスズキ・カルタスのTVコマーシャルの影響で(苦笑)“Shout”のほうが知名度があると思うけど、私はこちらのほうが好きです(笑)。
この曲がヒットした1985年の春といえば、私が富山高校の山岳部に入部した時期にあたり、富高山岳部の春合宿として(すなわち、私にとって初めての本格的登山となった)地元の大辻山登山に行ったのもちょうどこの頃。本格的登山経験が殆ど無かったというのに、連れて行かれた先は雪がまだ多く残る残雪期登山。キック・ステップを切りながら、ピッケルもアイゼンもなしに雪の斜面を登るのに当時は何の疑問も抱かなかったけど、今から振り返ると「何て恐ろしいことをさせられてたんだ!」と思わず青くなってしまう(笑)。あれから21年が経過し、あの頃よりも遥かに登山の知識も経験もあるけど、想い出に残る山旅のうちの1つです。また同じコースを歩けと言われたらヤだけど(笑)。
今でもこの曲を聴くと、1985年の春山の想い出が甦ってきます。
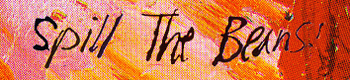
2006年4月(第67回)...ライド“ツイステレラ”(“Twisterella”)より
アルバム『ゴーイング・ブランク・アゲイン』(『Going Blank
Again』)収録...1992年作
【コメント】
'80年代末から'90年代初頭にかけてU.K.ロック・シーンで起こったムーヴメント(?)のひとつが、シューゲイザー。轟音ギター・ノイズを主徴としたサウンドで、マイ・ブラディ・ヴァレンタインや、ラッシュ、ペイル・セインツといったアーティストがその範疇で語られるワケだけど、そのシューゲイザーの主要バンドの1つがオックスフォード出身の4人組・ライド。シューゲイザーとしての評価からして言えば、彼らは1st『ノーホエア』で「終わった」のかもしれないけど、シューゲイザーからの脱却を謀り、サイケやアコースティック、プログレ風味などいろんなサウンドに挑戦し音が拡散し始めた2nd『ゴーイング・ブランク・アゲイン』のほうを私は好きで、よく聴いた。この“Twisterella”という曲は、シンプルなポップ・ソング。ライドはサウンドの拡散からメンバーの対立を招き、アルバム4枚残してアッケなく解散しちゃいましたが、もしも、ライドがこのポップ路線を突き進んでいたらどーなってたか興味はあります。
にしても、マーク・ガードナーと並ぶ2枚看板として、ライドの顔だったアンディ・ベルが今やオアシスのベーシストになり、すっかり『脇役』に徹してるのをみて、フクザツな気持ちになるのは私だけでしょーか?(苦笑)

2006年3月(第66回)...ザ・ウォーターボーイズ“ザ・ニュー・ライフ”(“The
New Life”)より
アルバム『ドリーム・ハーダー』(『Dream Harder』)収録...1993年作
【コメント】
マイク・スコット率いるザ・ウォーターボーイズが1993年にリリースした6thアルバム『ドリーム・ハーダー』の冒頭を飾る曲。
デビュー当時からのロック・サウンドから離れ、4th『フィッシュマンズ・ブルース』、5th『ルーム・トゥ・ローム』ではケルト音楽に傾倒していた彼が、再びロック・フィールドに戻って来た!...と、当時日本のロック・メディアでも好意的に捉えられていたアルバム『ドリーム・ハーダー』。なかでも、この“ザ・ニュー・ライフ”はロック・フィールドへの帰還宣言として、話題を集めてた。この曲の冒頭の歌詞にある「burn
one's
bridges」という言い廻しは「退却の道を断つ」、「背水の陣を敷く」といった意味で、このアルバムに込められたマイクの決意がよく表れてる...という見方をされてました。
私がこの曲をよく聴いてたのは、翌1994年の年明けのこと。1990年から4年間続いてた「3年生」を離れ、ようやく「4年生」に進級出来る見込みが立ってた頃で、「新しい人生が今始まる」ような気がしてたものだからさぁ〜(苦笑)。
ちなみに、この『決意表明』にもかかわらず、ウォーターボーイズは実質的にこのアルバムで最期。マイク・スコットはソロ・アルバムを細々と出してるけど、今なお「流浪」を続けている模様...(苦笑)。

2006年2月(第65回)...カルチャー・クラブ“君は完璧さ”(“Do
You Really Want To Hurt Me”)より
アルバム『ミステリー・ボーイ』(『Kissing To Be
Clever』)収録...1982年作
【コメント】
良くも悪くも'80年代を代表するアーティストの1つであるカルチャー・クラブが'82年の末から'83年の年明けに放ったワールドワイドなヒット曲。
この曲がシングル・ヒットする前、アルバム『ミステリー・ボーイ』がリリースされたばかりの時にはこの曲には“冷たくしないで”という邦題が付いてた。“Do
You Really Want To Hurt
Me”という原題を考えると、こちらのほうが邦題としては正しいんだろうけど、ちょうどこの頃“すみれSeptember
Love”のヒットで人気がピークにあった一風堂の見岳
章がこの曲を“君は完璧さ”というタイトルでカヴァーしたことがキッカケで、“冷たくしないで”から“君は完璧さ”に改題された。見岳
章によるカヴァーはまったくヒットしなかったけど、こうやってタイトルとして残ったことからすると、存在意義があったのかもしれない(苦笑)。
1983年当時、私は中学1年〜2年生。今でもだけど、当時もボーイ・ジョージ率いるカルチャー・クラブはイロモノ扱いされてて、仲間内でも好き嫌いがハッキリしてた。そんななか私はこの曲が大好きで、この度閉鎖が決まった『富山西武』の8Fのゲーム・コーナーへ友達と行った時にはジューク・ボックスに入ってたこの曲を何度も鳴らし、カルチャー・クラブ嫌いな友達に「嫌がらせ」をやった...そんな想い出があります(爆笑〜!!!)。

2006年1月(第64回)...ロケット・フロム・ザ・クリプト“ボーン・イン'69”(“Born
In '69”)より
アルバム『スクリーム、ドラキュラ、スクリーム!!』(『Scream, Dracula,
Scream!』)収録...1995年作
【コメント】
アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ出身のホーン隊を含めた6人組、ロケット・フロム・ザ・クリプトのメジャー・リリース第1弾『スクリーム、ドラキュラ、スクリーム!』に入ってる曲。スピード、J.C.2000、アポロ9、ペティX、N.D.、アトムといったメンバー名や、メンバー全員お揃いの衣装着たり、ヴィデオ・クリップが面白かったり...とコミカルな面もあったけど、硬派なパンクを聴かせるバンドでした。音楽に対する姿勢が真剣なあまり、かえってコミカルにみえたんでしょう。愛すべきバンドでした。
...というふうに「でした」と過去形で書いたのは、2005年に彼らの解散が発表されたから。1997年1年に恵比寿の狭いハコで観た彼らのライヴ(ちなみに、前座はKEMURI)や、苗場に場所を移してから初めての『FUJI
ROCK FESTIVAL』でオープニングを務めた時の演奏を観た者としては、彼らの解散のニュースは、一つの時代が終わったかのような感慨深くも淋しいものでした。
ちなみに、私も1969年生まれです(笑)。