
JASRACがうるさいので、歌詞と訳詞は省略させていただきます。

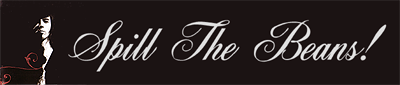
2008年12月(第99回)...アイ・アム・ゴースト“ディス・イズ・ホーム”(“This
Is Home”)より
アルバム『ラヴァーズ・レクイエム』(『Lovers'
Requiem』)収録...2006年作
【コメント】
バッド・レリジョンのMr.ブレットがオーナーってことで『メロコアの総本山』と看做されてる『Epitaph』レーベル所属の6人組、アイ・アム・ゴーストの1stフル・レングス・アルバム『ラヴァーズ・レクイエム』に収録されてる曲。『Epitaph』所属ということからメロコア・バンドに違いない!と思いきや、『Grind
House』の読者よりも『BURRN!』の読者にウケそうな、ゴスやメロコアからの影響が伺えるドラマティックなハード・ロックを演っている。紅一点のケリスが奏でるヴァイオリンがとても効果的で、そのヴァイオリンの音色のせいか、曲によってはイエローカードっぽく聴こえたりします(笑)。ヴァイオリストのケリスは、曲によってはリード・ヴォーカルのスティーヴとヴォーカルを分け合ってて、この“This
Is
Home”では、そのケリスのヴォーカルがとっても印象的です。特に、曲の終わりのほうの♪
isn't cold〜 isn't
co〜〜〜ld〜...というパートでの微妙な歌い廻しが、私は凄く気に入ってる(笑)。というふうに、アイ・アム・ゴーストというバンドでは、ケリスはキー・パーソンと思ってたんですが、1stアルバムのリリースに伴う過酷なツアーに耐え切れず、そのケリスがバンドを脱退...。その事実を知った時、アイ・アム・ゴーストというバンドへの興味が一気に醒めたよ...(苦笑)。
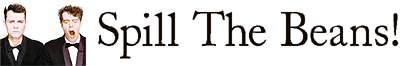
2008年11月(第98回)...ペット・ショップ・ボーイズ“哀しみの天使”(“It's
A Sin”)より
アルバム『哀しみの天使』(『Actually』)収録...1987年作
【コメント】
'80年代を代表するエレ・ポップ・デュオのペット・ショップ・ボーイズが、1987年にリリースした2nd『哀しみの天使』(原題『Acutually』)に収録されてる曲。1985年に大ヒット・シングル“West
End Girls”で華々しくシーンに登場した時には一部のメディア(『FM
fan』とか)に「一発屋」扱いされてたけど、21世紀の今でもしっかり生き残ってます。
ペット・ショップ・ボーイズといえば、今では『ゲイ・ユニット』であることがすっかり周知の事実となってますが、1987年当時はどうだったか?...ちょっと記憶にないんだけど、当時の私はこの曲を「ゲイのひとが書いた曲」とあまり意識せずに(もしくは、全く知らずに)聴いてたと思います。今、この曲の歌詞を「ゲイのひとが書いた曲」と念頭に置いたうえで改めて読み返してみると、とても意味深なことに気付かされます(苦笑)。この曲がホントにそーゆー意味を持つ曲かどうかは知りませんが...(苦笑)。

2008年10月(第97回)...オアシス“モーニング・グローリー”(“Morning
Glory”)より
アルバム『モーニング・グローリー』(『(What's The Story) Morning
Glory?』)収録...1995年作
【コメント】
1994年のデビュー・アルバム『オアシス』の大成功で、ブラーと共にブリット・ポップ・ブームの牽引役として音楽シーンの注目を集める人気ロック・バンドとなったオアシスが、ファンや音楽メディアからの期待が集まるなか、1995年10月にリリースした2ndのタイトル曲。他のロック・バンド(インスパイラル・カーペッツ)のローディーを経験するなど、雌伏の下積み時代が長かったノエル・ギャラガーが、弟とバンドを結成した(っつうか、弟のバンドを乗っ取った)途端、デビュー・アルバムで絵に描いたような大成功を収めた...という経緯があるゆえ、ミョーに説得力のある歌詞。1995年といえば、大学を7年かけてようやく卒業した私が、就職し、新たな第一歩を踏み出した時に当たり、「今までのオレとは違う。新しい何かをやってやる!」という気概に満ちあふれてた時期。そんな気分にこの曲はよくハマリました。10月頃は朝、クルマのカー・ステレオで『モーニング・グローリー』聴きながら毎日出勤し、「オレも、オアシスみたいに天下獲ってやるぞ〜!!!」と無意味に気分を高揚させてたし、この曲を聴いて、「今の自分はまだ眠ってるだけで、目が醒めた時には何か凄いことが出来るんだ」という根拠もなく確信してました(苦笑)。
あれから13年。未だに私は、目が醒めてないし(爆笑〜!!!)、大器晩成型ですら無かったよーです(苦笑)。
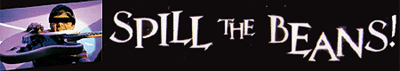
2008年9月(第96回)...スティーヴ・ミラー・バンド“アブラカダブラ”(“Abracadabra”)より
アルバム『アブラカダブラ』(『Abracadabra』)収録...1982年作
【コメント】
『ジョーカー』や『鷲の爪』、『ペガサスの祈り』などのアルバムで'70年代に大成功を収めてたスティーヴ・ミラー・バンドが1982年に放った大ヒット曲。全米チャート(『Billboard
Hot 100』)では、1982年を代表するヒット曲であるサバイバーの“Eye Of
The Tiger”とシカゴの“Hard To Say I'm
Sorry”(“素直になれなくて”)の間隙をついて1週のみ1位を獲得。日本の洋楽チャートでもサバイバーとシカゴにアタマを抑えられ1位にはなれなかったものの、(文化放送『オール・ジャパン・ポップ20』において)2位に輝くなど、それなりのヒットを記録。しかし、2008年の今となっては、サバイバーとシカゴの曲がいまだに名曲として語られ続けてるのに対し、この曲の扱いは地味です。ハッキリ言って。
1982年といえば、私が洋楽に目覚めた『洋楽元年』。耳にするもの全てが新鮮に聴こえてたため、1982年の洋楽ヒット曲にはどの曲にもイロイロと思い入れがあるものだけど、小学・中学時代の友達のKクンがこの曲に合わせて「アブラカダブラ」の踊り(勿論、Kクンのオリジナル)を踊ったりして『仲間ウケ』してた...という想い出があるので、特に思い入れが深い。
この頃のスティーヴ・ミラーのアチ写は、サングラスかけてたり、『目伏せ』をされてたり...と、瞳をみせないモノばかり。特に『目伏せ』までするアーティストは(今でも)珍しいので、今でも印象に残ってます。
今や日本ではすっかり「“Abracadabra”といえば米米CLUB」ということになってますが、以上のようにこの曲には思い入れがたくさんあるため、私は今のこのような風潮には我慢ならないのです。

2008年8月(第95回)...テキサス“サマー・サン”(“Summer
Son”)より
アルバム『ザ・ハッシュ』(『The Hush』)収録...1999年作
【コメント】
こーゆーバンド名だけど、実はスコットランド・グラスゴー出身のテキサスの5thアルバム『ザ・ハッシュ』に収録されてる曲。紅一点のヴォーカリスト、シャーリーン・スピテリを中心とした彼らは、もともとアメリカ市場ウケするアーシーなロックを演り、ジョン・メレンキャンプと全米をツアーするバンドだったハズなのに、どんどん一般大衆向けポップ・ロックに移行していき、全英では4th『ホワイト・オン・ブロンド』で大きな成功を収めた。この成功作に続いてリリースされた5th『ザ・ハッシュ』では、アルバムのアートワークにセクシーなシャーリーンの写真をフィーチュアすると同時にシャーリーン以外のメンバー写真が消え、あたかもシャーリーンのソロ・プロジェクトのような感じになってしまった。サウンドも「女性ソロ・シンガーのアルバム」という感じで、バンドらしさは希薄。このポップなアルバムは前作に引き続き全英で大ヒットを記録した。
このアルバムが日本でリリースされたのは、『FUJI ROCK
FESTIVAL』(以下、『フジ・ロック』)が苗場で初めて開催された頃。朝の早い時間帯は(会場から遠いとの理由でこの年1回のみで移転となり、もう二度とキャンプすることはないであろう、スキー場の斜面にあった)キャンプサイトで、『フジ・ロック』の会場で買った『rockin
on』1999年9月号を読んで時間を潰してたんだけど、その号にシャーリーンのインタヴューが載ってたのをよく覚えてます。この年の『フジ・ロック』にはテキサスは出演してませんが、この曲を聴くと1999年の『フジ・ロック』を思い出します(苦笑)。

2008年7月(第94回)...ザ・ホワイト・ストライプス“デッド・リーヴス・アンド・ザ・ダーティー・グラウンド”(“Dead
Leaves And The Dirty Ground”)より
アルバム『ホワイト・ブラッド・セルズ』(『White Blood
Cells』)収録...2002年作
【コメント】
このサイト界隈では『激ブス』と呼ばれてる(苦笑)姉のメグ・ホワイト(ds.)と弟のジャック・ホワイト(g.,
vo.)のホワイト姉妹によるベースレスの2人組、ザ・ホワイト・ストライプスの2002年リリースの3rdアルバムにして本邦デビュー・アルバムの冒頭を飾る曲。
これまでのロックの常識を覆すような2人編成でシーンに登場した彼ら。御多分に漏れず、私も彼らの存在を知ったのは2002年の3rdアルバムリリース直後&『フジ・ロック』出演前。『RED
MARQUEE』に出演する彼らの予習がてらに彼らの音楽に初めて触れて、そのサウンドの粗さとは対照的にキャッチーで親しみ易いリフを持つ楽曲群にすっかり魅せられてしまった。この年の『フジ・ロック』で一番印象に残ってるのは彼らのライヴと少年ナイフです(笑)。
その後、このアルバムの勢いのまま3枚のアルバムをリリースし、『グラミー賞』を取ったりと音楽シーンの牽引役として突っ走ってきてましたが、メグが急性不安神経症になたったためライヴ活動を休止してしまいました。もう、彼らのライヴが観れなくなるかと思うと、そして、メグのシンプルなドラミングが観れないと思うと実に淋しいものがあります。
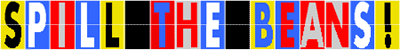
2008年6月(第93回)...VERSUS“Never
Be OK.”より
アルバム『Two Cents Plus Tax』収録...1998年作
【コメント】
BLOODTHIRSTY
BUTCHERSとの交流で知られるアメリカのバンド・+/-(プラス/マイナス)の前身バンドともいえる4人組のギター・バンド、VERSUSが1998年にリリースしたアルバム『Two
Cents Plus Tax』に収録されてる曲。
VERSUSはフィリピン系アメリカ人のBaluyut兄弟と女性ベーシストの
Fontaine Toupsを核とした4人組。バンドのリーダーはRichard
Baluyutで、彼が殆どの曲のリード・ヴォーカルをとってるけど、この曲ではベースの
Fontaineがヴォーカルをとってます。初期のVERSUSにはソニック・ユースを思わせるアングラ臭が漂ってたけど、作品を重ねるごとに洗練され次第にポップになっていき、2000年には彼らの最高傑作ともいえる『Hurrah』をリリース。やるべきことはやり尽くしたと感じたのか、その後彼らは活動停止状態となり、メンバーたちは+/-やそれぞれのソロ・プロジェクトに移行していった。
この曲は『Two Cents Plus
Tax』のなかでもポップであり、『Hurrah』の収録曲でも聴けるサーカスみたいな男女混声コーラスもあったりして(苦笑)、最高傑作『Hurrah』への布石になったのかなぁ...と思ってます。VERSUSについてはこちら→も参照下さい。

2008年5月(第92回)...RUSH“ブレイヴェスト・フェイス”(“Bravest
Face”)より
アルバム『スネークス&アローズ』(『Snakes &
Arrows』)収録...2007年作
【コメント】
RUSHが2007年にリリースした18枚目のオリジナル・スタジオ・アルバム『スネークス&アローズ』に収録されてる曲。
1985年の『パワー・ウィンドウズ』リリース後にRUSHのファンになった私は、1987年の『ホールド・ユア・ファイアー』以降のアルバムはみんな日本盤発売日にはしっかり入手してた。が、この『スネークス&アローズ』の時には、レコード屋で予約しようとしたら「初回入荷分はすでに予約で埋まってて、次の入荷待ちになりますが...」とゆわれ、RUSHファンになって初めて発売日にRUSHの新譜が手に入らないかもしれないという危機が訪れた。どーしてもRUSHの新譜を発売日に聴きたいので、『iTune』で発売日ダウンロード予約したり、複数のレコード店に予約を入れてみたり...と必死にあがいた。結局、ふだんは「『イオン高岡』のタワーレコードなんて『タワレコ』じゃない!」と馬鹿にしてた『TOWER
RECORDS』高岡店が入荷日にたくさん入荷してくれてたお蔭で、なんとか遅れることなく入手することに成功した。なんだかんだ言っても、『タワレコ』は偉大だった(苦笑)。
この曲は、このアルバムの中で私が一番好きな曲。このアルバムに伴うツアーじゃあ、この曲を演らなかったみたいだけどね。
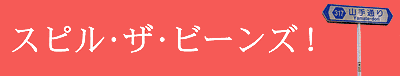
2008年4月(第91回)...椎名林檎“闇に降る雨”より
アルバム『勝訴ストリップ』収録...2000年作
【コメント】
今は「東京事変」というバンドで活躍する椎名林檎ががまだソロ・アーティストだった頃(苦笑)の2000年春にリリースした2ndアルバム『勝訴ストリップ』に収録されてる曲。
衝撃のデビュー・アルバム『無罪モラトリアム』により『新宿系』アーティストとして一躍シーンの話題を攫い、その後リリースされたシングルののプロモーション・ヴィデオの「看護師コスプレ」(“本能”)や「真っ二つベンツ」(“罪と罰”)の影響か、社会現象とすら呼べるほどの盛り上がりをみせ、多くのフォロワーを生んだ、ブームの最高潮時にリリースされたのが、『勝訴ストリップ』。周囲のあまりの期待の大きさの反動か、某音楽雑誌の読者人気投票で2000年度『金返せアルバム』の1位に輝くなど、「期待ほどじゃなかった」というバッシングも受けたけど、私はこのアルバム、大好きです(笑)。
この“闇に降る雨”という曲、♪雨だろうが〜運命(さだめ)だろうが〜...という言葉遊びみたいな歌詞が面白く、特に気に入ってます。バレリーナが出てくるプロモーション・ヴィデオも面白かった。

2008年3月(第90回)...ザ・ダークネス“ゲット・ユア・ハンド・オフ・マイ・ウーマン”(“Get
Your Hands Off My Woman”)より
アルバム『パーミッション・トゥ・ランド』(『Permission To
Land』)収録...2003年作
【コメント】
2003年のロック・シーンで大きな話題となった新人バンド、ザ・ダークネスのデビュー作『パーミッション・トゥ・ランド』に収録されてる曲。『着陸許可』なるアルバム・タイトルに合わせてか、全裸の女性がU.F.O.の着陸誘導をするジャケットが凄くおバカ。
ヘヴィー・メタル/ハード・ロック系の人気が停滞気味の2003年のU.K.ロックシーンに登場した彼ら。往年のフレディー・マーキュリー(クィーン)を思わせる気持ち悪いファルセット・ヴォイス、そしてゼブラ柄のレオタード姿で歌うヴォーカルのジャスティン・ホーキンスのインパクトでシーンの話題をさらい、一躍『U.K.ハード・ロックの救世主』と祭り上げられるようになった。日本でもジャスティンのヴォーカル・スタイルや衣裳について面白おかしく音楽メディアで取り上げられ、話題沸騰となった。彼らの将来に亘っての成功は約束されてたかにみえたけど、2ndアルバム・リリース後のツアー中に、突如看板ヴォーカリストのジャスティンが脱退! ザ・ダークネスは空中分解してしまった...。残された3人はバンド名を改名し、活動を継続してるけど、ジャスティンのインパクトが強すぎた故に、前途多難な感じ...。
この曲を初めて聴いたのは、彼らの話題がひと段落した2004年3月頃、愛車『Anonymous
2112』号のカーステで。ジャスティンのファルセット・ヴォーカルがあまりにもキモチ悪く可笑しいので、クルマを運転しながら笑い転げてました(危ねぇ...)。

2008年2月(第89回)...RUSH“ザ・ビッグ・マネー”(“The
Big Money”)より
アルバム『パワー・ウィンドウズ』(『Power
Windows』)収録...1985年作
【コメント】
RUSHの13枚目のアルバム『パワー・ウィンドウズ』に収録の曲で、このアルバムからの先行シングルとしてカットされ『Billboard』のHOT100で、TOP40入り目前まで上昇したヒット曲。
当時、私は『全米TOP40』にハマっており(苦笑)、『Billboard』のHOT100でTOP40入りした曲をエア・チェックしてカセットテープに録音することを趣味にしてた(苦笑)。TOP40入りした曲を漏れなく録音しようとするならば、TOP40入りまぢかの曲も予め録音して揃えておけば漏れは少ない。そういうことで私は当時隆盛を誇ったFM雑誌の『FM
fan』掲載の『Billboard』のHOT100チャートをみながらFMの番組表をチェックするのが日常となっていた。そんな1986年1月のある日、FMの番組表をチェックしてたら、『Billboard』のHOT100でTOP40入りまぢかなRUSHの“The
Big
Money”という曲がFM富山の深夜の某番組でかかることを発見! 録音すべく準備し、曲がかかるのを待ち構えていた。そして、番組表どおりその深夜の番組でかかった“The
Big
Money”...この時、私は初めてこの曲を聴いたんだけど、あまりに凄さにド肝を抜かれた。壮大なスケールを持ち、ドラマティックな曲展開。これまでこんなの聴いたこと無い!...と思った。翌日からは、録音した“The
Big
Money”をテープが伸びるまで繰り替えし繰り返し聴くようになった私、すっかりRUSHのとりこになってしまい、あれだけ執着してた『全米TOP40』にも興味が無くなり、TOP40入りした曲をエア・チェックして録音するという趣味もヤメました。RUSHがあれば、他は何も要らない...って感じで(笑)。
毎年2月くらいになると、RUSHに夢中になってたあの頃の感覚を思い出します(笑)。
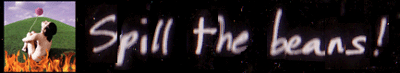
2008年1月(第88回)...ポーラ・コール“スローイング・ストーンズ”(“Throwing
Stones”)より
アルバム『ディス・ファイア』(『This Fire』)収録...1996年作
【コメント】
アラニス・モリセットの大ヒットにより1990年代の半ばからは女性シンガー/ソングライター・ブームが起こり、「アラニスに続け!」とばかり、多くの女性シンガー/ソングライターがデビューした。ポーラ・コールの場合、アラニスの大ヒット以前にデビュー・アルバム『ハービンガー』をリリース済みだったけど、商業的成功には程遠く、ピーター・ガブリエルの『シークレット・ワールド・ツアー』に参加し、ケイト・ブッシュの代わりに“Don't
Give
Up”を歌ったりするなど下積みの時代が長かった。が、アラニスの大ヒットでシーンの状況は一変。1996年にリリースした2nd『ディス・ファイア』からは“Where
Have All Cowboys Gone?”や“I Don't Want To
Wait”のシングルがヒットを記録。お蔭でポーラは2枚目のアルバムだというのに『グラミー賞』のブライテスト・ホープを受賞してしまった。その後、サラ・マクラクラン主宰の女だらけのフェスティヴァル『リリス・フェア』に積極的に関与したり...と、90年代の残りは快進撃を続けた。
この“Throwing
Stones”は何かに追われてるかのような切迫感/緊迫感が印象的な曲。(オンナのドロドロとした情念をオモテに出すアラニス型のシンガーが受けた時代のせいか、)歌詞もコワいです...(苦笑)。